今シーズンのスケジュールも約半分を消化しました。
Bリーグ公式から発表されているスタッツやアドバンスドスタッツを中心にでチームの現状を分析していきたいと思います。
※各スタッツの計算式は BasketBallReference 参照
今回はPart2ということで、前回の分析記事と関連が強い内容となっています。前回紹介した内容については省略している部分もありますので比較しながら見てみてください。
現在のロスター
# 年齢 pos 身長
【上位スタッツ】
リーグ上位8位以内にランクされているスタッツ
1試合平均FT試投数 : 17.1本 B1全体6位 B1平均:16.1本
1試合平均TO数:12.0 B1全体7位 B1平均:12.62
DR獲得率(全ディフェンスリバウンドシチュエーションにおいての獲得割合):70.08% B1全体8位 B1平均69.9%
eFG%(3Pの価値を高めFG%へ反映させた、実質シュート決定率):49.64% B1全体7位 B1平均:49.28%
PACE(マイボールから、シュートを1本打つまでの攻撃回数):73.3回 B1全体8位 B1平均:72.91
アウェイゲームeFG%:51.84% B1全体4位 B1平均:49.63%
アウェイゲームTS%:54.30% B1全体4位 B1平均:52.60%
【下位スタッツ】
リーグ下位6位以内にランクされているスタッツ
1試合平均失点:78.8pts B1全体14位 B1平均76.08pts
1試合平均3pt成功数:5.9本 B1全体16位 B1平均:7.21
対戦相手のeFG%(対戦相手の平均eFG%) : 50.86% B1全体14位 B1平均:49.42%
1試合平均スティール数:5.4本 B1全体16位 B1平均:6.54本
フリースロー決定率:67.08% B1全体17位 B1平均:72.10%
1試合平均アシスト数:11.6本 B1全体15位 B1平均:13.22本
OR獲得率(全オフェンスリバウンドシチュエーションにおいての獲得割合) :28.3% B1全体13位 B1平均30.00%
DRtg(100ポゼッション当たりの失点):93.4pts B1全体15位 B1平均:90.40pts
NetRtg (Ortg-Drtgの差分):-3.3 B1全体13位 B1平均:-0.19
AS%(チームのシュート成功数に対する、アシストの割合):31.69% B1全体17位 B1平均:37.12%
【ランクアップスタッツ】
~15試合の時点から、3ランク以上上昇したスタッツ
1試合平均失点:B1全体17位→ B1全体14位
3Pt決定率: B1全体14位→ B1全体11位
対戦相手のeFG%(対戦相手の平均eFG%) : B1全体17位→ B1全体14位
1試合平均フリースロー試投数:B1全体9位→ B1全体6位
【ランクダウンスタッツ】
~15試合の時点から、3ランク以上下降したスタッツ
フリースロー決定率: B1全体14位→ B1全体17位
1試合平均アシスト数:B1全体9位→ B1全体15位
DR獲得率(全ディフェンスリバウンドシチュエーションにおいての獲得割合) :B1全体5位→ B1全体8位
平均観客動員数:B1全体4位→ B1全体7位
AS%(チームのシュート成功数に対する、アシストの割合):B1全体14位→ B1全体17位
【スタッツで観る注目選手】

ジェイソンウォッシュバーン
16.9pts 8.5reb 1.1ast 0.8stl 0.9blk
USG26.5%で中盤戦の横浜1stオプション&ポイントリーダーの選手です。
TS59.9%の効率性もチームNo1

川村卓也
15.8pts 3.4reb 3.4ast 0.8stl 0.1blk
対戦チームに徹底したマークに遭い、各シュート決定率が下がったためポイントリーダーとはなりませんでしたが、得点はチームNo2。徹底マークを逆手に取りAST数値を上昇させています
【スタッツで観るチームの特徴】
第15節終了時点での横浜は、前回のブログとほぼ同じく、速いペースで速攻主体のオフェンスチームであると言えるでしょう。
スクリーンもありますが、基本的にはあらるポジションで1on1を仕掛けます。
特にオフェンスの鍵となる川村選手や、細谷選手の1on1から活路を見出す戦術を取っています。
1/3対京都戦の第3Qから2つご紹介します
【1/3 京都戦第3Q残り3:20】
右のウィングの川村選手がパスを受け、3ptライン沿いにドリブル→京都の佐藤選手がダブルチームに入る→川村選手が空いたウォッシュバーン選手へパスを出しミドルポストからレイアップ
【1/3 京都戦第3Q残り1:35】
右のハイポストパーマー選手へボールを入れる→月留選手のハンドオフスクリーンを使い竹田選手がボールを受ける→左ウイングの細谷選手へパスと同時に月留選手が左のハイポへ移動しHornsの形へ→ゴール下からから左のショートコーナーへ山田選手がカッティング→細谷選手から山田選手へパス→山田選手はカウンタードリブルでマークマンを抜き去りレイアップ
上のように、スクリーンは(月留選手のハンドオフスクリーン以外)あまり使わず、1on1で二人惹きつけてからのパスでオープンを作ったり、空いたスペースへダイブしてインサイドや3ptシュートのパターンを多用します。
ディフェンスについては、オンボールスクリーンに対する守り方は(ヘッジ、カバー、ローテーション)に対する意思疎通は序盤戦に比べいいコンビネーションが取れていますが、オフボールスクリーンに対するディフェンスに若干の穴が見られます。
例えば、同じく1/3の京都戦第3Q残り5:52〜4:30のわずか1分少々の間に3回もオフボールスクリーンからオープンショットのシチュエーションを作られてしまっています。
【1/3 京都戦第3Q残り5:52】
細谷選手のマークマンである内海選手へ、川村選手のマークマンである川島選手がフレックススクリーン→細谷選手がスクリーンにかかる→川村選手はそのまま川島選手のディフェンスへ(川島選手に二人付いている状態)→そのすきに内海選手がペイントへカールカットする→右のペリメタでボールを保持するコッツァー選手から内海選手へパス→内海選手レイアップ
【1/3 京都戦第3Q残り5:10】
右のウイングから川島選手と佐藤選手のP&R→川村選手上手くファイトオーバー→川島選手が左
エルボーのコッツァー選手へパス→そのまま川島選手は、右のローポストへロールした佐藤選手へダウンスクリーン→スクリーンを利用して佐藤選手がペリメータへ→コッツァー選手は佐藤選手へパス→佐藤選手ワイドオープンショット
【1/3 京都戦第3Q残り4:30】
エンドラインからスローイン→コッツァー選手が岡田選手へスクリーン→岡田選手がスクリーンを使う(竹田選手がスクリーンにかかる)→細谷選手がカバーリングに行く→岡田選手へパスが渡りワイドオープン3pt(細谷選手間に合わず)
スクリーンへのカバーというよりも、ボールに対する注目度合いが高いためスクリーンが行われている事自体への反応が遅れているように感じます。
これらにしっかりコンテストショットできれば、対戦相手のeFGをより下げることができると思います。
もう一つの懸念点としては、3pt決定率が挙げられます。これは確率のよい選手が細谷選手と川村選手であるためチェックが厳しく、タフなプルアップジャンパー多いために起こっています。細谷選手がオンボールの際には、川村選手がオープンでキャッチアップシュートできるスクリーンプレーの連携を高めるなど修正次第で確率を大きく上げることができるでしょう。
ウイングからのオンボールスクリーンやインサイドのコンビネーションパターンが1Q当たり2〜3回増えるだけでより効率的なオフェンスができ、ORtgを高くすることができるでしょう。

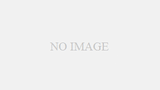
コメント